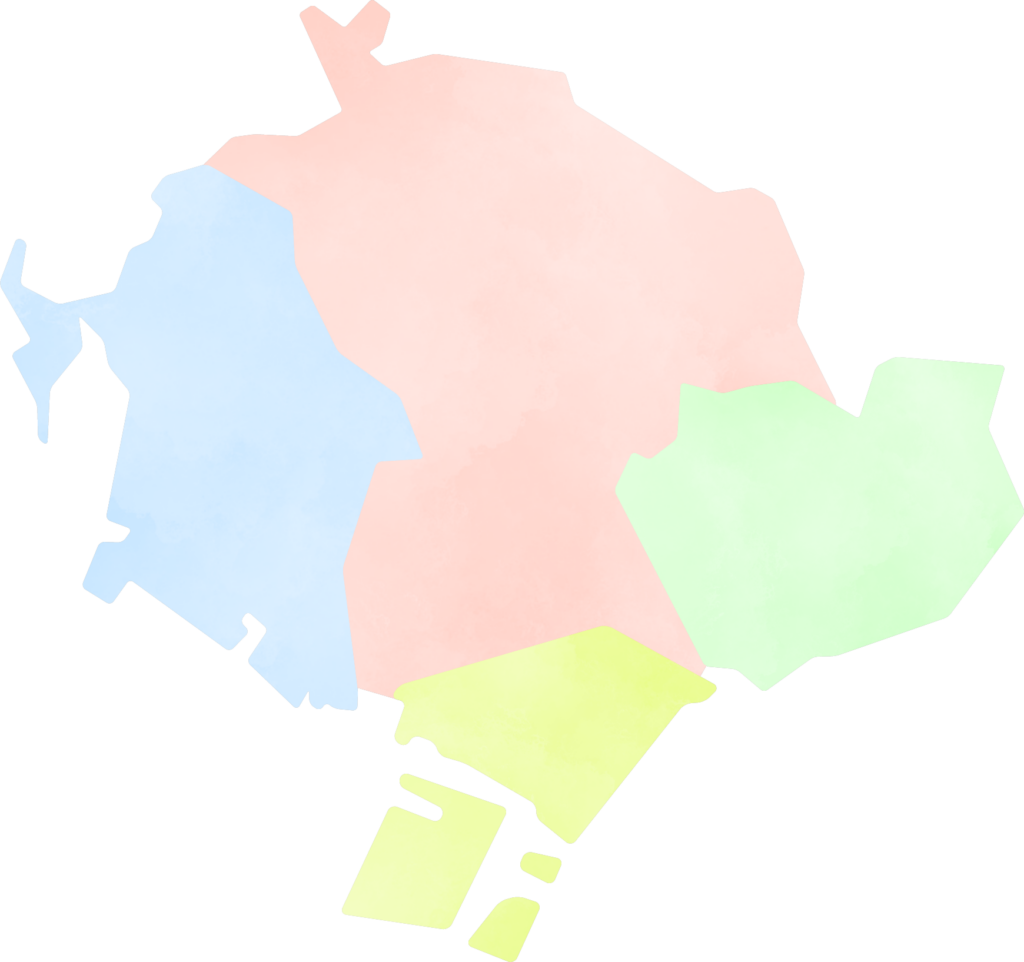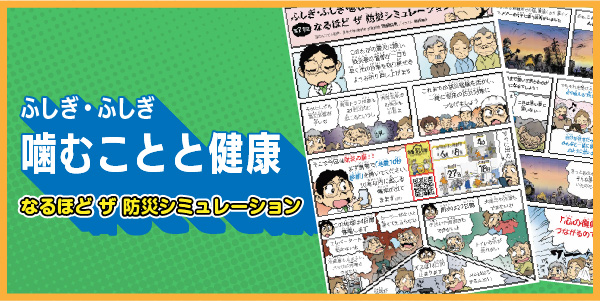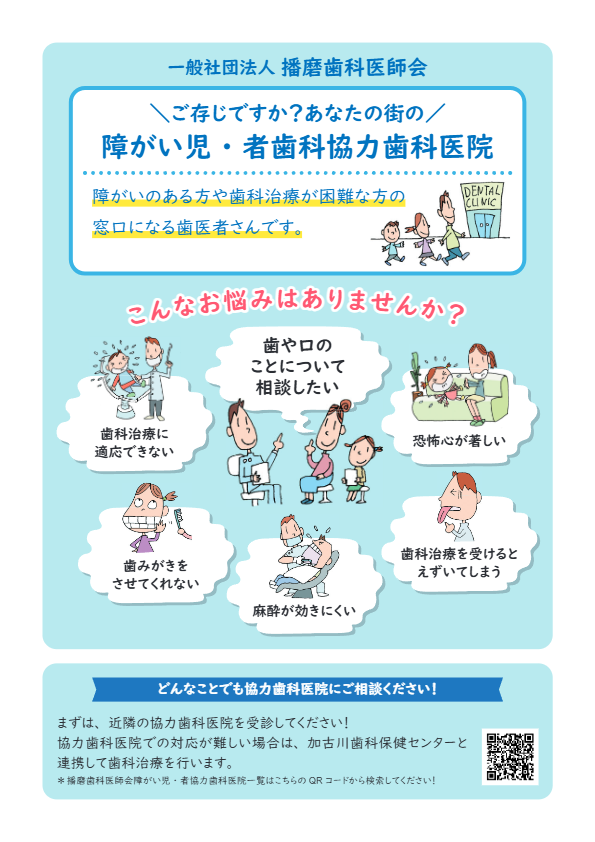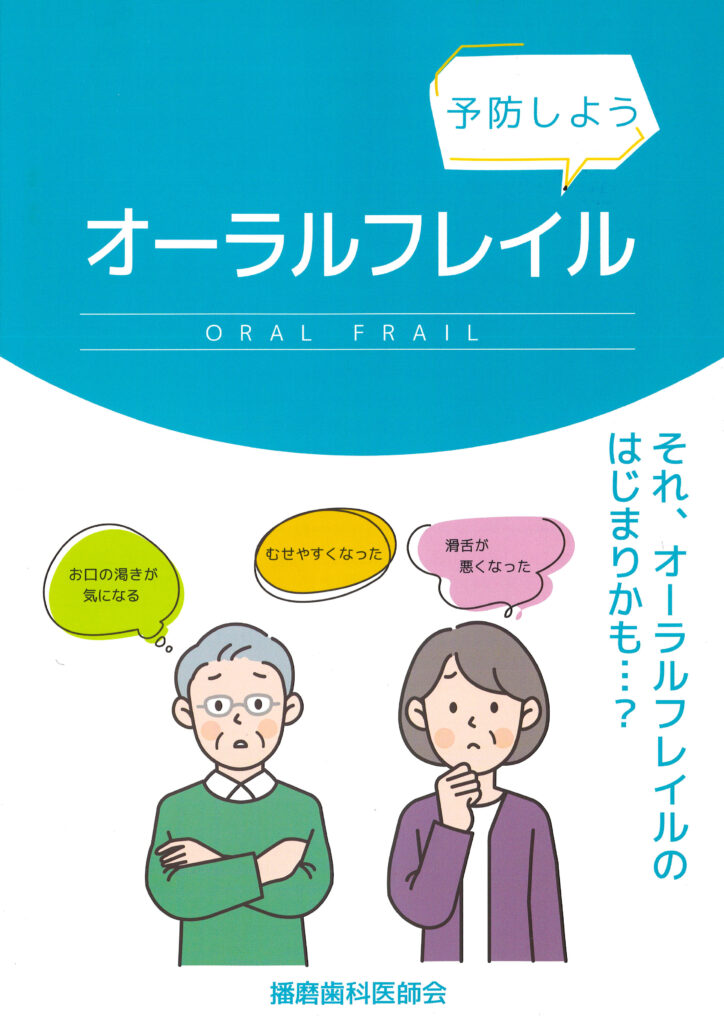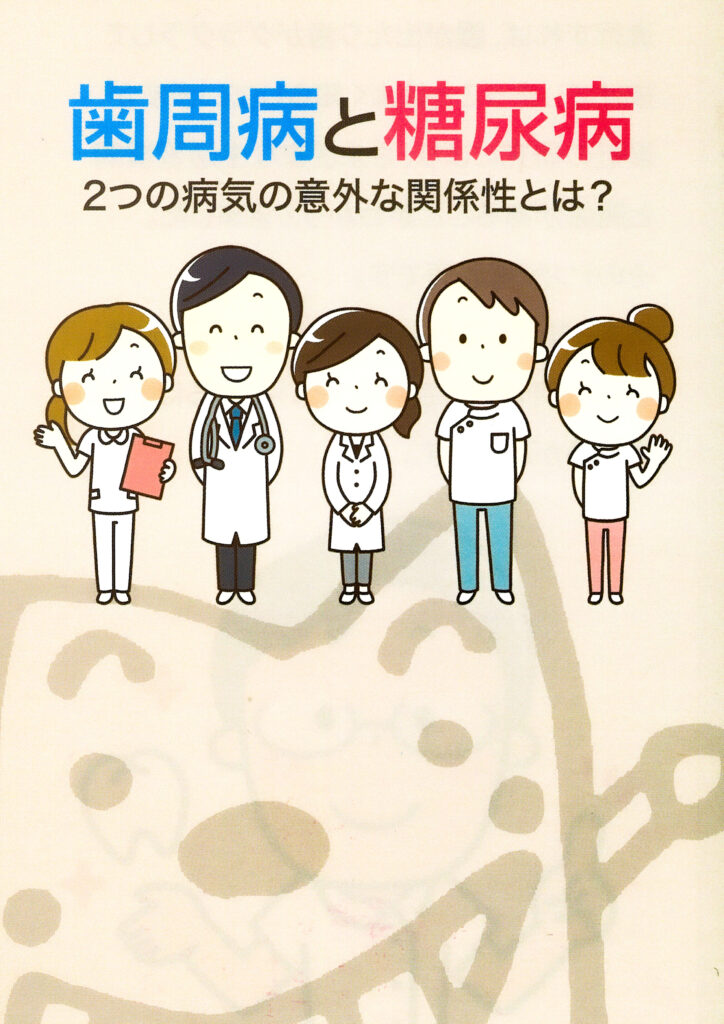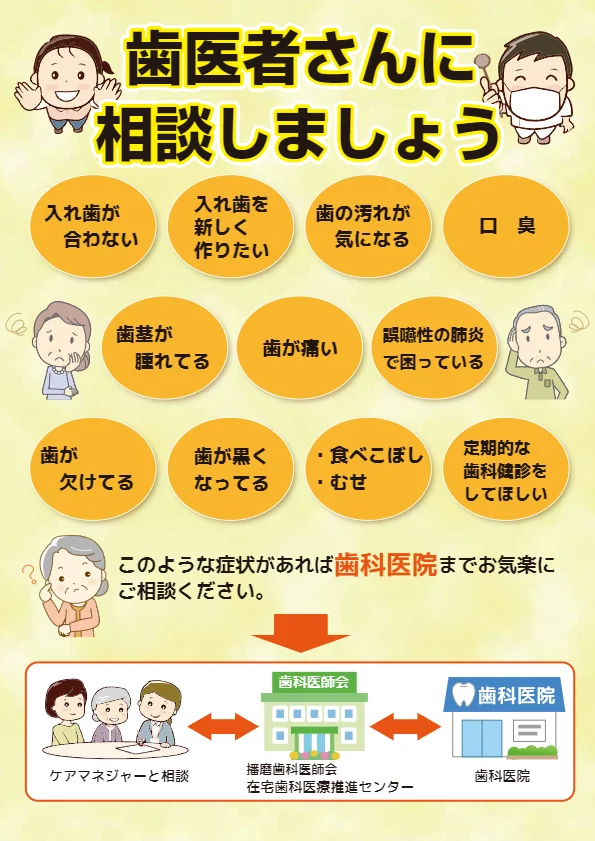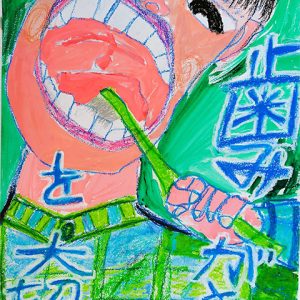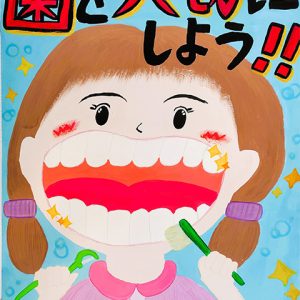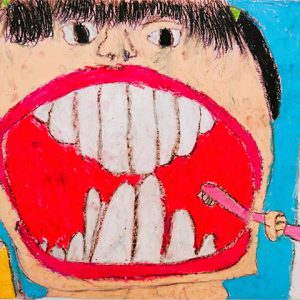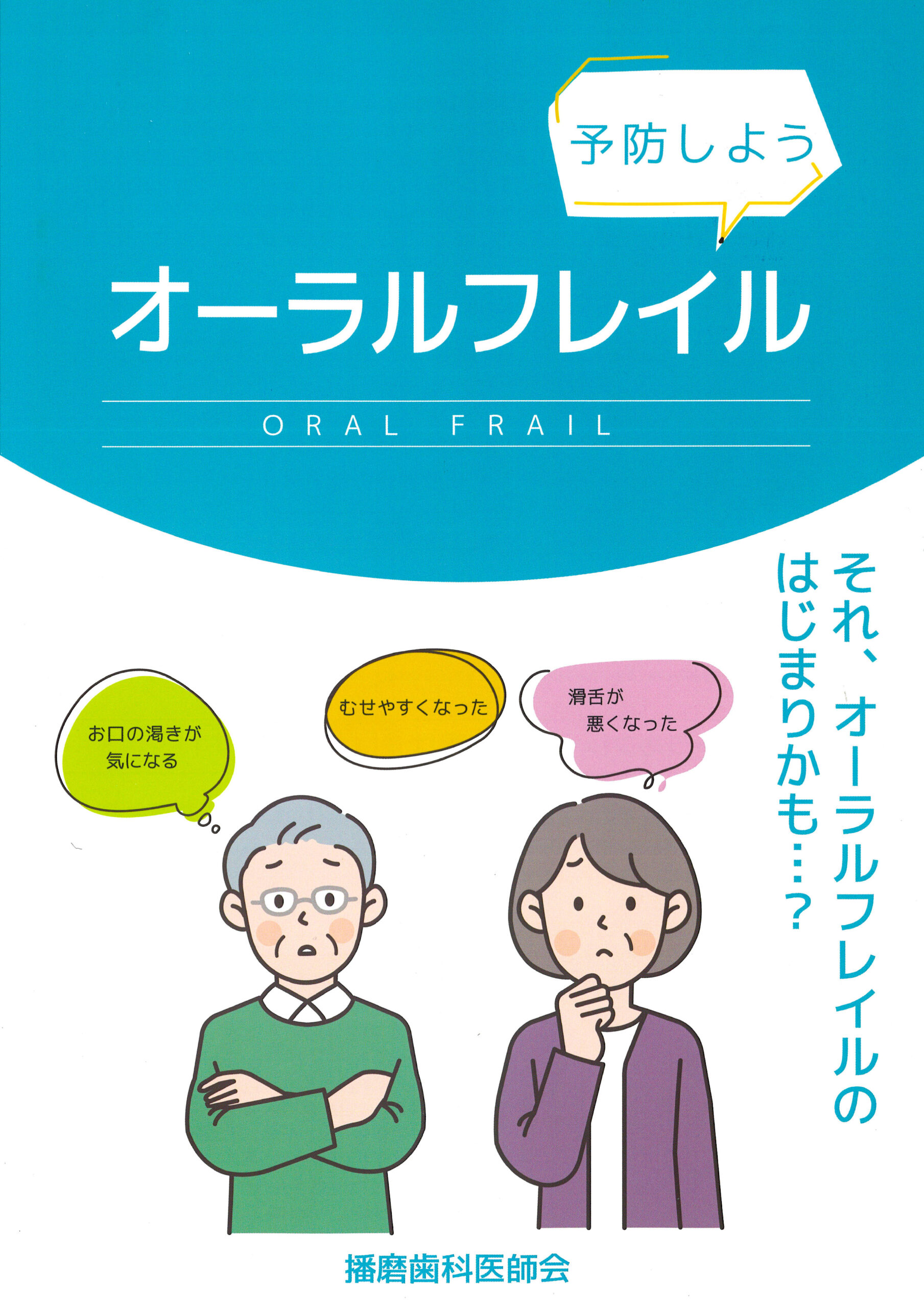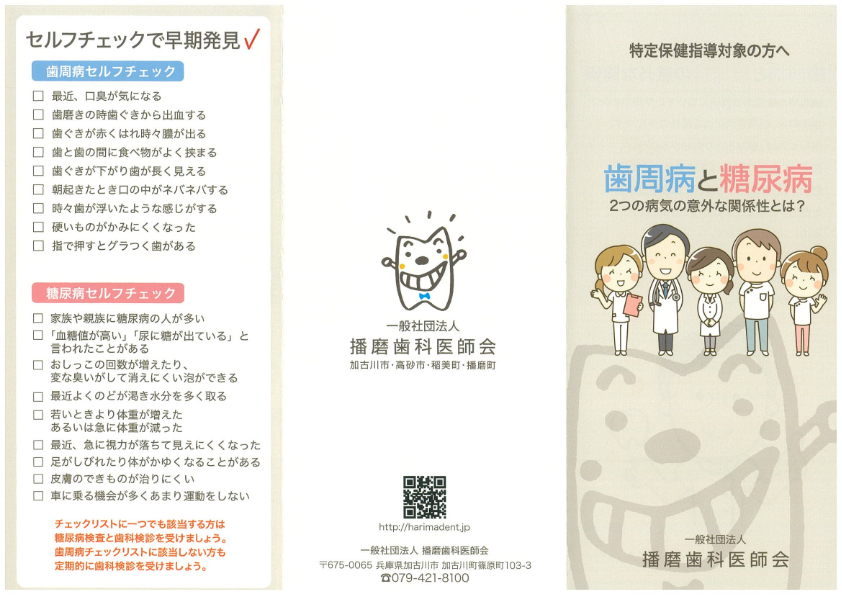新着コラム
- 歯や口腔について知ろう
Tooth Contact Habit(TCH:歯牙接触癖)とは
- 歯や口腔について知ろう
お薬(骨吸収抑制薬)と顎の骨の健康について
休日歯科診療
休日、急に歯の治療が必要となった方へ
障がい児・者歯科診療
障がいのある方で歯科診療が困難な方へ
訪問歯科診療
寝たきりなどで通院することが困難な方へ